恐竜絶滅「すす」が原因?東北大など新説
http://this.kiji.is/132287447396861435
記事によると
・今から6600万年前に起きた恐竜など生物の大量絶滅は、地球に小惑星が衝突して舞い上がった「すす」による気候変動が原因だったとする新説を、東北大大学院理学研究科と気象庁気象研究所が発表した
・大量絶滅を引き起こした要因として最も有力なのはメキシコ・ユカタン半島に落下した小惑星原因説だが、小惑星の衝突と気候変動の因果関係を巡っては、巻き上げられた「ちり」が太陽光を遮って起きた地表寒冷化、大量発生した酸性雨による海水の酸性化など諸説あった
・東北大の海保邦夫教授らは、カリブ海のハイチとスペインで小惑星衝突後に堆積した地層からすすを採取し、成分を分析。炭化水素の一種「コロネン」の含有率が高いことを突き止めた
・コンピューターで当時の気象変動を再現すると、舞い上がった大量のすすが上空約10~50キロの成層圏に7~8年とどまり続けて太陽光を吸収。気温が低下して海水の蒸発量が減り、降水量が激減したために植物が枯れて食物連鎖が崩れたという
・ちりの飛散は、短期間で収まって大きな気候変動には至らないという。海保教授は「もし、小惑星の衝突地点が海だったら、恐竜は絶滅しなかったかもしれない」と話している。
1. この話題に反応する名無しさん
すす許さん
2. この話題に反応する名無しさん
恐竜が絶滅した原因より、巨大化した要因を知りたいです。
酸素濃度が濃かったから?
3. この話題に反応する名無しさん
イースⅧってこの説を参考にして作ったんじゃないかって思う感じだよね(笑)
4. この話題に反応する名無しさん
ちりとすすでは結構ちがうのか。まだまだ学ぶことがたくさんあるな、この世は。
5. この話題に反応する名無しさん
塵と煤に違いがあった事に、驚いた。
原因と結果が同じなら、新説と言う程の驚きは無い。
6. この話題に反応する名無しさん
「コロネン」てなんやネン?
過去にはこんな説も
【恐竜絶滅は氷河期が原因じゃなかった?千葉工業大学が世界で初めて別の「絶滅説」を肯定する実験に成功!!】
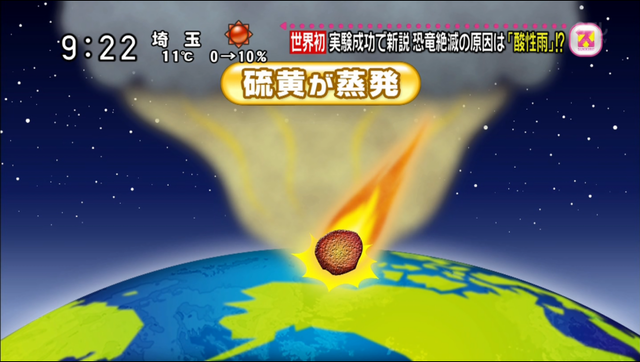


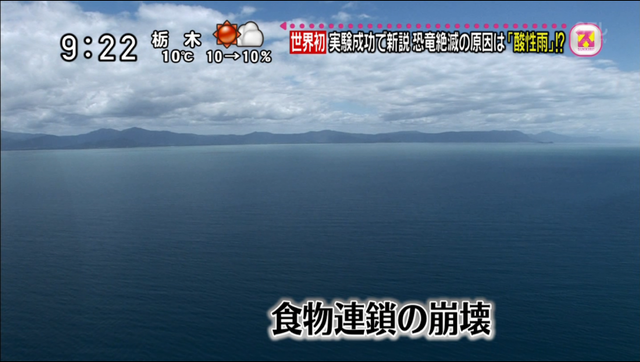
いろんな説考えるもんだなぁ
どれが真実なのかはわからないけど、1匹くらい現代まで生きててほしかった


ポケットモンスター サン・ムーン ダブルパック 【初回限定特典】どうぐ「モンスターボール」100個 シリアルコードチラシ 2枚(各ソフトに1枚ずつ同梱) 【Amazon.co.jp限定特典】オリジナルマイクロファイバーポーチ2種(イエロー/ブルー)
Nintendo 3DS
任天堂 2016-11-18
売り上げランキング : 81
Amazonで詳しく見る




世の中アホだらけ
ばかじゃねーの
新説と言うには無理がある
みたいな灰じゃあ死なないで!(´・ω・`)
塵説での矛盾が煤説だと説明できるんだから新説でしょ
↑
要約:言ったもん勝ち
前からあるだろこれ
掘削調査で判明 国際チーム】
メキシコ・ユカタン半島の巨大隕石落下跡は、
約6500万年前(中生代白亜紀末)に恐竜などの生物が
大量に絶滅した原因などではなく、
大量絶滅の時期より約 3 0 万 年 も古いことが、
研究成果は米科学アカデミー紀要に発表される。
この「チチュルブ・クレーター」は1990年代初めに発見され、直径は推定180~280㎞。
形成時期は従来、大量絶滅が起きた白亜紀と新生代第3紀の境界(KT境界)の
前後20万年以内とされ、ほぼ一致するとの見方が有力だった。
日本も参加する「国際陸上科学掘削計画」(ICDP)の支援を得て、
クレーターの中心から約60㎞の地点を掘削。
KT境界は地下794.1mと、隕石の衝突跡より約50センチも上にあることを突き止めた。
さらに、堆積物の分析など5種類の方法で詳細な年代を特定した。
その身体の小さな哺乳類が俺らの祖先なんだろ
さらにKTバウンダリー形成の500万年前にはとっくに恐竜が世界規模で絶滅の危機に瀕していた。
というのもなぜかこの500万年の間にはたった12種類しか恐竜の化石が発掘されていないからだ。
(それ以前の地層からは何百種類と恐竜の化石が発掘されている)
アンキロサウルスやハドロサウルス、イグアノドン・オリエンタリスなどが含まれるが
いずれも化石に「奇妙な共通点」がある。
呼吸器だ。
その奇妙な共通点見れば何が原因で恐竜の数が激減したのかおのずと原因が判る。
だからいって、それが恐竜絶滅に繋がっているとは断定し難い。
昔は恐竜は冷血動物で寒さに弱いとされていたため、
その頃はまだこの説は信憑性があった。
しかしいまや恐竜は温血性で、
従来考えられていたのと異なり寒さに強い事がわかってしまった。
世界中の恐竜がなぜか一匹残らず絶滅してしまったのに
変温動物で恐竜以上に寒さに弱いトカゲやヘビやカメやカエル、
非常に体の大きなワニなどすが、
絶滅する事もなくのうのうと生き延びた事の説明がまったくつかない。
あまり餌を必要としない犬程度の大きさしかいないものも沢山存在していた。
それ故に「餌の減少のため全恐竜が一時に絶滅してしまった」という
一見説得力がありそうな説は、その実穴だらけのお粗末な代物にすぎない。
鰐や蜥蜴などが古代のままの姿をとどめあえるのに、
そのままでも生存共存に勝ち残れるであろう優れたデザインの恐竜だけは
ただの一種すら残さず鳥に変化してしまったというのはそもそも無理がある。
また最初の恐竜が出現した頃の三畳紀には、既に鳥の祖先と思しき化石が存在しており、
それ以降の時代も鳥の化石は多々発掘されている。
要するに鳥と恐竜はほぼ同時期に出現した近縁種で、以降長く共存した別個の種である事が明らかだ。
そんな大昔のこと分かるわけない
恐ろしい程のバカだ…
酸素濃度が濃かったから?
恐竜が飛躍する切っ掛けとなった前の絶滅で酸素濃度が10%以下となり、そんな中気嚢システムを持つ恐竜が元気だったんだよw
その後1億年位は酸素濃度10%前後
>また、「恐竜は今は鳥類として生き延びている」という妄説もあるが
笑ってたw
どっちが妄説だよw
もう恐竜から鳥が派生したのは定説だぞwww
だって絶対に答えでないじゃん
どうなっても絶対仮説でしかないんだからな
そんなの研究するぐらいならタイムマシンの研究した方が解明の近道じゃね?
答えなんて出なくていいんだよそれが金になるんだからw
スス様のおかげという事か
うーんその分け方は違うかなと
明暗を分けたのは体の大きさで
チビが生き残っただけだし
宇宙スケールからしてみたらとんでもない確率だろうなあ
そのへん飛んでるじゃん。
鶏なんか、ズームすると恐竜にしか見えない。
旧世界の神々だよ
過去の説と言ってる事は同じじゃんか
一匹てバカじゃないのww
適当な仮説を事実であるかのように語ってるような気しかせんのだが
酸素濃度だけでは無理、自転速度が速く重力と遠心力のバランスが今と違い重力は軽かったのと
月が今よりももっと近かったために潮の満ち引きが数十~百メートルもあった
これにより翼竜は待ってるだけで山の上に登れ、巨大恐竜は浮力で簡単に移動出来た。
しかもそれが8時間ごとに来る、あとは恐竜の遺伝子は巨大化が止まらない仕様だったのだろう。
もう少し勉強しろ
隕石衝突による事象全てが原因だろうに。
どれか一つが原因ではなく、それらが複合的に絡み合った結果なんだと、小学生の頃か何度もそういう特番にツッコミ入れてたなぁ。
DNA鑑定でも裏付けが取れてるしな
だいいち、参照してる記事が古すぎるな、この人
古生物学なんて10年で常識変わるぞ
たぶん違うんだろうな
今迄の事実が違っても新発見って形で誤魔化せるんだから、失敗がない職種でもある。
そうニートのお前には絶対無理な職業だよ