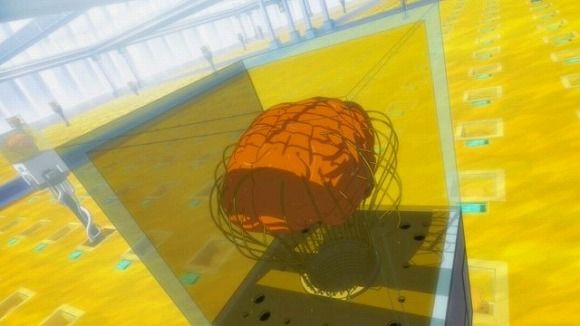
近年のAIの進化は実は理解されていない。
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
ChatGPTを筆頭に、信じられないレベルでAIが進化している。
そう、本当に信じられないレベルなのは、なぜAIがこんなにも「急激に」質が良くなったかを、誰も説明できないからだ。
おそらく発明した研究者本人たちですら。
どういうことか。
1/n
近年のAIの進化は実は理解されていない。
ChatGPTを筆頭に、信じられないレベルでAIが進化している。
そう、本当に信じられないレベルなのは、
なぜAIがこんなにも「急激に」質が良くなったかを、
誰も説明できないからだ。
おそらく発明した研究者本人たちですら。
どういうことか。
AIの精度を定量化したとき、数年前までは研究の進化と共に、少しずつ精度があがっていった。
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
研究の進化とは
1. モデルやアルゴリズムの進化
2. 計算量の増加
3. データ量の増加
などだ。10年ほど前にAIがもてはやされた時は、Deep Learningといったモデルの進化が重要だった。
2/n
反面、計算量やデータ量の増加によって、「驚くべき」進化があるとは誰も思っていなかった。
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
計算量を倍、倍としていけば、それに応じて精度がちょっとずつ上がっていく、と想定したからだ。そこには驚きはないはず。
今までの論文ではそうだった。むしろ量の増加による精度改善は飽和していた
3/n
ところがこの数年で研究者はびっくりする結果を目にする。
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
なんと、計算量やデータ量を増やしたところ、
完全に飽和していたと思われた精度が、ある量を境に、急激に改善したのだ。
下記の図の横軸が計算量、縦軸が精度だ。
まじか、とみんな思った。
4/n pic.twitter.com/V51NVCDBWf
ところがこの数年で研究者はびっくりする結果を目にする。
なんと、計算量やデータ量を増やしたところ、
完全に飽和していたと思われた精度が、
ある量を境に、急激に改善したのだ。
下記の図の横軸が計算量、縦軸が精度だ。
まじか、とみんな思った。
上記のグラフは、複数ステップの計算、大学レベルの試験、文脈の言葉の意味を読み取る精度だ
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
この急激なAIの進化は他のところでも観測されており、
例えば「質問の仕方を変えればAIのアウトプットが圧倒的によくなる」という現象も、ある一定の計算量がなければ起こらない
5/n pic.twitter.com/Z2XfPL3gLf
この現象は実はいまだに理解されていない。
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
なぜこんな転換点が存在するのか。
実は人類がこのような現象に出会ったのは初めてではない。
これこそが物理学においてこの100年間研究されてきた「相転移」という現象なのだ。
6/n
AIに戻ると、
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
去年はComputer scienceの領域で、AIの学習で量が質を変える現象が「発見」された年だった。
今年からはこの現象を説明し、より加速度的にAIが進化する時代に突入する。
第1次、2次産業革命が各種ノーベル物理・化学賞の仕事に支えられたとすれば、それがまたやってくる
10/n
今成果を出しているAI研究者は物理で言えば実験科学者に近い。
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
これからはより深い理論構築ができるAI研究者がどんどん出てくる。
興奮の渦だ。
11/n
上記の現象についてはGoogle researchのブログに詳しいので是非読んでみてほしい。12/nhttps://t.co/M9Bp1leIDs
— Takuya Kitagawa (@takuyakitagawa) January 29, 2023
この記事への反応
・ おびただしい数の会話をしていて、
その内容を完全に全部覚えているのだから
あっという間に進化するでしょう。
昨日かなり専門的な会話をしてたら、回答が的確で、
なんなら人間と会話するよりも盛り上がったわ。
・他の動物と似たような脳にもかかわらず
人間だけが高度な知性を獲得したのも、
学習量が閾値を超えたからなんだろうな。
・ ニューラルネットがこんな将来性あるとは思わなかったな。
物量は全てを解決する的な。
脳を模してるってのも間違いじゃないのかも。
・過学習して終わりかと思ったらダブルディセントがあったからでしょ
・まとめるとデータがある量を超えると一気にAIの能力が上がる、
温度を上げても何も変化のない水が100度になった途端
水蒸気に変わるのと一緒
これは相転移と物理では一般に言われる事で、
受験勉強の砂を噛むような数ヶ月が
ある日一気に身を結び成績が上がる事と全く同じ事が、
AIでも起きている。
要するに
「かがくのちからってすげー」
ってことやな(小並)


- カテゴリ

はちま起稿
ゲーム全般カテゴリ 2 位
過去記事の閲覧ができます
 ライブドアアプリでフォローする
ライブドアアプリでフォローする








1. はちまき名無しさん
これはまだ序章に過ぎない